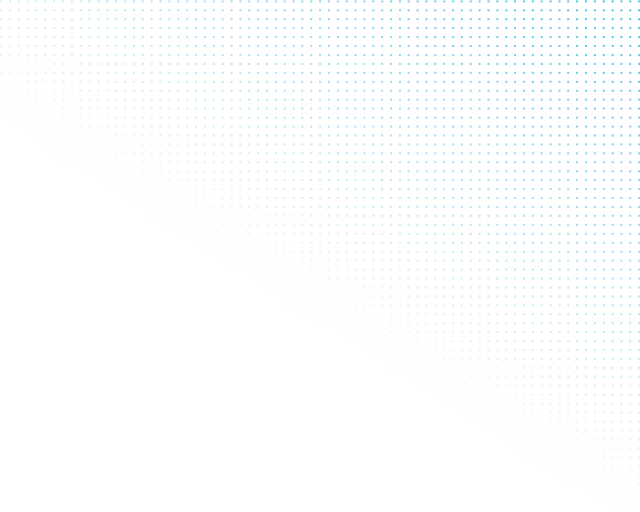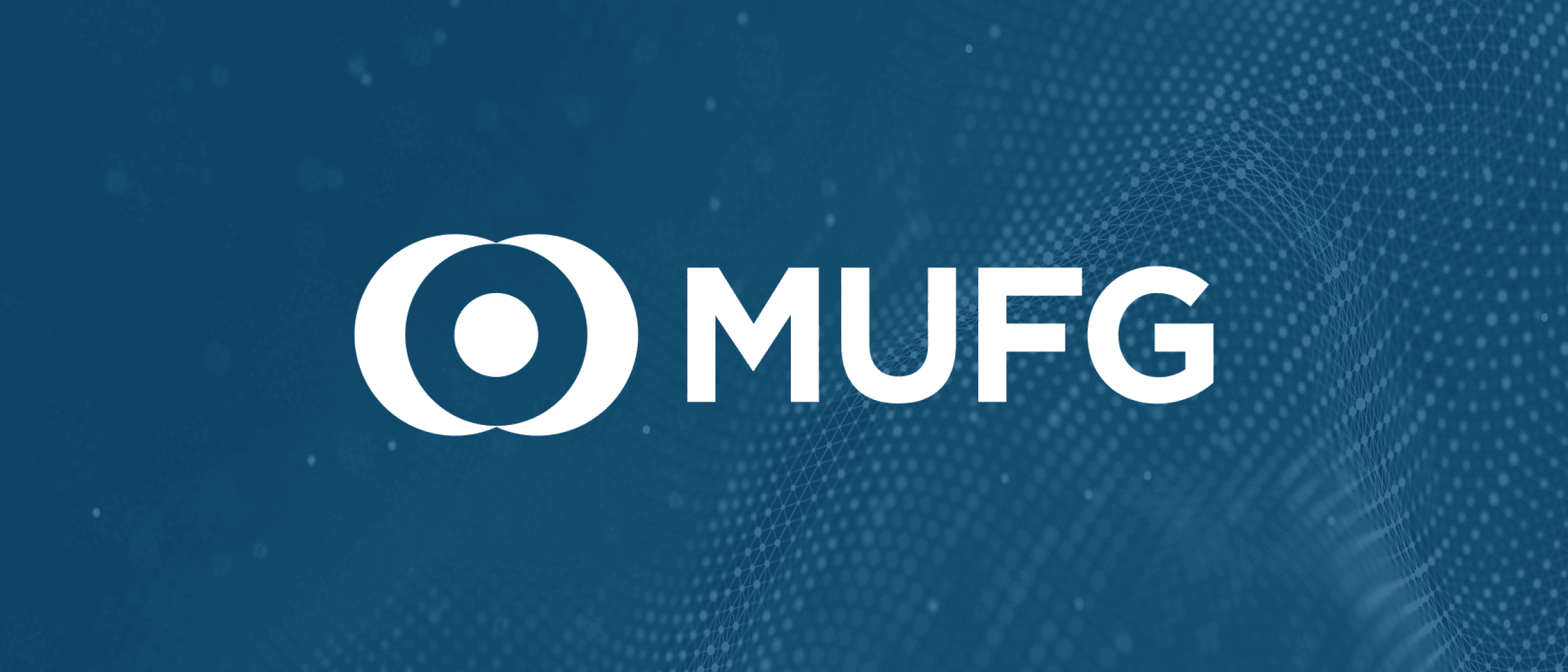
カスタマーストーリー
全社共通の顧客データ基盤にSnowflakeを採用、 事業部を超えた施策の比較や分析スキル共有 各種システムの垣根を超えたデータ活用を推進
パナソニックコネクトが挑む、事業部間連携と顧客情報サイロ化の解消。Snowflakeによる全社共通の顧客データ基盤と従業員の意識改革。
KEY RESULTS:
400時間
データ共有に必要な時間を削減
240→10分
各システムを横断したKPI集計を省力化


業種
Manufacturing所在地
東京都中央区Snowflakeを採用した全社共通の顧客データ基盤で、事業部を超えた施策比較とデータ活用を推進
パナソニック コネクトは2022年の事業会社制への移行により誕生した事業会社の一つで、B2Bソリューション領域を担う。データ利活用では、事業部の独立性が強く、各事業部間での連携強化が課題になっていた。また顧客体験向上の観点では、データ管理ツールや組織(営業/マーケ/CS)による顧客情報のサイロ化も大きな課題だった。専門的な知識がなくても扱えることを意識したSnowflakeによる全社共通の顧客データ基盤は、サイロ化解消だけでなく、データに関する従業員の意識改革にも大きな役割を果たそうとしている。
Story Highlights
- 共通の顧客データ基盤による各施策の効果の可視化
- 顧客管理・営業管理ツールを超えた一気通貫の顧客管理
- 顧客データ基盤(CDP)構築による顧客体験の向上
サイロ化したデータ運用が生んだデータ利活用の平準化という課題
パナソニック コネクトは2022年の事業会社制移行により生まれた、パナソニックホールディングス傘下の8つの事業会社の一つである。コネクティッドソリューションズ社を中核として誕生した同社は、溶接ロボットから物流、流通分野の各種ソリューション、レッツノートで知られる法人向けPC事業、航空分野にいたるB2Bソリューションを提供する役割を担っている。
従業員数は約28,200名。国内に14の事業所と10の関連会社、海外に23の事業所を展開し、パナソニックによる大型買収がニュースにもなったサプライチェーンマネジメントソフトウェア大手のブルーヨンダー社や物流システム大手のゼテス社などのグローバル企業も傘下に含まれる。
データ利活用において同社が直面した課題は、マーケティングにおける顧客データ利活用の平準化だった。複数の事業部がそれぞれマーケティング部隊を備えるが、独立性が強く、データ活用の度合いにばらつきが目立ったことがその理由である。各事業部門のマーケティング活動を支援する役割を担うデザイン&マーケティング本部 データアナリティクスエキスパートの岩本 章伸氏はこう説明する。
「各事業部のマーケティング担当者の分析スキルや意識の違いの背景には、事業部の垣根だけでなく、顧客情報をはじめとするマーケティングに関連するデータの共有が図られてこなかった点にもありました。事業部門それぞれがマーケティング施策を打ちKPIを測定してきましたが、これまで比較検討の材料は部門内に限られていたことはその分かりやすい例です。また事業部ごとのデータ利活用は、類似したグラフやBIダッシュボードの乱立など、業務の重複化にもつながっていました」
また、事業部によるデータ利活用は、データのサイロ化にもつながっていた。「顧客データが部門システムに分散して蓄積されることで、複数事業部で当社と取引するお客様に一貫した顧客体験を提供することが困難になっていました。また、マーケティング担当が分析に必要なデータを発見しても、管理者を特定することが困難で、利活用が難しいという問題もたびたび生じていました」(岩本氏)
これらの問題は、同社がデータドリブンマーケティングを追求する上で避けて通ることができない課題になっていた。
MAツールのデータを蓄積する新たな基盤にSnowflakeを採用
パナソニック コネクトがまず行ったのは、各事業部のWebページやデジタル広告の実績データを手動で収集し、事業部を横断してデータを閲覧できる共通のBIダッシュボードの構築だった。それにより、事業部間のデータ活用の格差や重複業務の解消に一定の役割を果たしたが、部門データ収集の更新頻度が月1回に限られるなど、手作業による対応には限界があった。
「次に取り組んだのは、マーケティングオートメーション(MA)ツールのMarketoのデータのBIダッシュボード化でした。当社はMarketoを全社導入しており、獲得リードを一元管理し、メール配信などの施策を行っています。従来のように手動で月1回データ更新を行っていては、施策のPDCAを行うスピード感に間に合いません。そこで私たちはMarketoのデータを自動的に蓄積する新たな仕組みを構築することにしました」(岩本氏)
その基盤として同社が採用したのがSnowflakeだった。選定の中心的な役割を担ったIT・デジタル推進本部 データアーキテクトマネージャーの渡邉 勇太氏はその理由をこう説明する。
「2021年5月に岩本さんから相談を受けた際、コネクト全社で共通の(1つの)データ基盤(DWH)が必要であるという要望をいただきました。データ活用を成功させる上でデータ基盤は重要成功要因の一つと定義していましたので、すぐに具体的な検討を開始しました。データ基盤の大事な要件として、1運用負荷が低いこと、2スキルレベルを問わず誰もが使えるデータ基盤であること、3当社のネットワークポリシーに合うように標準的なプロトコル(HTTPS)で通信ができること、4コネクト標準の BIツールであるPower BIやTableauとの組み合わせが容易であることと定義しました。それらを要件の軸として、上市されている主要なクラウドデータ基盤を比較検討した上で、特に使いやすさを高く評価してSnowflakeを選択しました」
メール開封状況など、リアルタイムでMarketoが収集するデータを1日1回、Fivetranを介してSnowflakeに集約し、扱いやすい形へと一次加工を行なった上でTableau Cloudにデータを抽出。各事業部門のマーケティング担当者がブラウザ上で最新データの閲覧を可能にすることが新データ基盤の基本的な仕組みとなる。またマーケティング担当者が見ておくべき情報を6種類のダッシュボードに整理して提供することで、誰もが確実に必要なデータにアクセスできる環境を整えた点も注目すべきポイントだ。
顧客の反応がリアルタイムで把握できる環境の実現は、岩本氏が当初から目指してきた事業部間のマーケティング施策共有にもつながった。
「ダッシュボードの作成に合わせて、各事業部のマーケティングKPIの統一化も行ったことで、各事業部が行う施策が同じ物差しで比較できるようになりました。それは社内のより優れた取り組みに目を向ける意識改革にも確実につながっています」(岩本氏)
新しい仕組みの導入は、必ずしもうまくいくとは限りません。CDP構築では小さくスタートし、効果を検証した上で次のステップに進みたいと考えましたが、専用ツール導入はスモールスタートが難しいのが実情です。私たちが求める運用に最もマッチしたのが、柔軟なスケールが可能なSnowflakeでした」
岩本 章伸氏
大幅なデータ統合工数削減を実現利活用の一層の推進を図る
同社の全社的なデータ活用の第二段階になるのが、部門横断での顧客情報を統合するカスタマーデータプラットフォーム(CDP)構築である。
「CDP構築の狙いは、大きく二つあります。一つはマーケティング施策の売上貢献まで含めた全体把握です。見込み顧客のリード獲得から受注までの一連のプロセスは、段階が進むにつれ見込み顧客が減少する漏斗型で表されます。各段階のKPI進捗を把握するには、マーケ部門が管理するアクセス解析ツールやMAツール、営業部門が管理する営業支援システムなど複数のシステムのデータが必要で、当社の場合、Adobe Analytics、Marketo、Salesforceのデータを別々に参照する必要が生じていました。もう一つが顧客体験向上という観点です。Marketoのデータはマーケティング部門が保有しているデータになりますが、それ以外にSalesforceに蓄積される多様な商談管理情報やサポートサービスの利用履歴など、さまざまな顧客データが社内に蓄積されています。現在私たちが目指す期待以上の顧客体験を実現する上で、社内の多様な顧客データを一元管理する新たな仕組みが不可欠でした」(岩本氏)
コネクトCDPと名付けられた顧客データ基盤の構築には、専用ツールも含め、多様な選択肢があった。その基盤としてSnowflakeを採用した理由を岩本氏はこう説明する。
「新しい仕組みの導入は、必ずしもうまくいくとは限りません。CDP構築では小さくスタートし、効果を検証した上で次のステップに進みたいと考えましたが、専用ツール導入はスモールスタートが難しいのが実情です。私たちが求める運用に最もマッチしたのが、柔軟なスケールが可能なSnowflakeでした」
またコネクトCDPに格納されるデータ管理を、ビジネス部門とIT部門の混成チームが担うことも注目したいポイントだ。
「ビジネス部門の『こういうデータが欲しい』というニーズに、ビジネスに関する深い知識を持たないIT部門のスタッフのみで対応するのは難しいのが実情です。一方でデータ加工や外部のデータの取り込みなどにはIT部門のスタッフの存在が不可欠です。そこで私たちはデータ基盤を管理する部門とは別に、IT部門、マーケティング部門、営業部門のスタッフが参画する『CDPデータマネジメントチーム』と名付けたチームを立ち上げ、データ基盤上のCDPの運用を行っています」(岩本氏)
Snowflakeによる一連の仕組みの効果としてまず挙げられるのが工数の削減である。同社の試算では、Marketoのデータの自動収集により、事業部間のデータ共有に要する時間が年ベースで400時間削減されたという。また以前は月4時間程度かかっていたSalesforce、Marketo、Adobe Analyticsを横断したKPIの集計が10分程度で完了するようになった。
同様に、Salesforce、Marketo、AdobeAnalyticsのデータがリアルタイムで確認できるようになったことも重要なポイントだ。これにより、マーケティング部門と営業部門の情報共有が促進されることは間違いない。
生成AIを利用したソフトウェアの開発期間の圧縮とコストを大幅に削減
生成AIの活用は今後の大きな課題の一つだ。
「当社ではLLMモデルの独自の運用を開始していますが、まだコネクトCDPのデータをLLMから呼び出すという状態には至っていません。まずはCDPに限らずSnowflakeに蓄積した構造化データをAIエージェントから呼び出すことを実現したいと考えています。データのさらなる全社的な活用には、ユーザーが業務の中で身近に使うことになるAIエージェントの存在が大きな役割を果たすことになると認識しています。ユーザーがデータ利活用しやすい環境の実現するために、今後のSnowflakeの機能強化に期待しています」(渡邉氏)
同社は、生成AI活用を含め、Snowflake上に構築したCDPを活用することで顧客解像度を高めることを目指している。
「CDP によって、オンライン上の顧客の動きが見えるようになったことは営業部門からも高く評価されています。今後は部門を超えたCDP活用をさらに進めたいと考えています。当社に限らず、全社的なデータ利活用はビジネス部門のユーザーのデータリテラシー向上が大きな課題ですが、AI により、例えば顧客の興味・関心を言語化することも可能です。これまでデータアナリストが行っていた作業を自動化し、ビジネス部門がよりデータを活用しやすい仕組みを今後構築していきたいですね」(岩本氏)
30日間の無料トライアルを開始する
Snowflakeの30日間無料トライアルで、他のソリューションに内在する複雑さ、コスト、制約の課題を解決するデータクラウドを体験できます。